ハイケ・B・ベテルマーカー/酒寄進一・訳『ヒトラーに愛された女 真実のエヴァ・ブラウン』レビュー
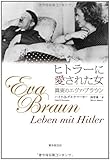
- 作者: ハイケ・B・ゲルテマーカー,酒寄進一
- 出版社/メーカー: 東京創元社
- 発売日: 2012/01/11
- メディア: 単行本
- クリック: 2回
- この商品を含むブログを見る
・100字レビュー
世界征服を企む権力を欲した男アドルフ・ヒトラーの「平凡な野望」は、最も身近な愛人の決断によって終止符を打たれた。彼と結婚した翌日に自殺した元祖「ヤンデレ」エヴァの独占欲は、独裁者よりも独裁的に思える。
・長文レビュー(約4,200字)
チュニジアやエジプトにリビアと世界中の独裁政権が倒された「革命ブーム」の昨今、日本の政権が自民党から民主党に変わったのも、海外ではその一環に思われていて、特に有名だった独裁者の一例として、いまヒトラーに関する書物を読むことは大切に思える。
いまだと北朝鮮が最もヒトラー率いるナチ政権に近い「完璧さ」を持っているように感じられる。彼の手腕はあらゆる面において「完璧」だった。そしてその「完璧さ」ゆえに破滅したのである。崩壊の兆候を察し、自ら命を捨てることで彼を夢から目覚めさせたのが、愛人エヴァ・ブラウンだった。
表紙の写真はソファに腰かけて眠っているように見えるヒトラーと、微笑を浮かべてそれを見つめる23歳年下の愛人・エヴァの横顔である。ページを開くと冒頭にも写真が5枚あり、1枚は遠景のため表情は分かりにくいが、他の3枚は屈託のない笑顔であり、残り1枚は何があったのか大きく口を開け驚いている。
彼女がヒトラーと写っている写真は表紙の他にもう1枚あって、友人の幼い二人の娘と共にいるところだが、俯き加減のヒトラーは難しい顔をしている。それに対して、やはり横顔のエヴァは、幼女の手を握りながら微笑みかけている。ヒトラーもその子らの手を握っているけれど、何を考えているのか分からない感じである。
これらの写真から戦火における悲壮感のようなものはエヴァには感じられないが、いずれもヒトラーは疲れ切った雰囲気で、写真を撮られるために表情を作っていない。
もともと彼自身が作り笑顔のできる器用な人間ではなかったのと、人に見られていることを気にする必要のないプライベートな空間だったことが、その理由だろうか。けれどもエヴァはそういう場面においても、常に笑顔だったのだ。
かつて彼女は実に平凡な女性であり、人前に出ることを好まない奥ゆかしい人だったとされてきた。その実像が本書では多方面から検証されるが、むしろ非凡な根性と政治性に長けた女性に思えてくる。だからこそ彼女は「非凡な権力を欲した平凡な男」ヒトラーに愛され続けることができたに違いない。
独裁者に寄り添い続けたエヴァの物語は、ヒトラー及びナチ政権の動向と複雑に絡み合っていて、そこに彼女の影を追い続けた本書の情報量は濃密なものであり、簡単に説明するのは難しいが、ヒトラーにまつわるあらゆるエピソードが詰め込まれている点において、一心同体といえよう。
本書はヒトラーが権力を得ていく過程、そして独裁者になってからの交友関係や私生活、更にはナチ政権下のドイツで女性がどのように暮らしていたかというフェミニズム的な観点も含まれ、二人の出会いから戦後の遺体発見まで、あらゆる側面から関係を暴きだす実に手の込んだ労作である。
ヒトラーは基本的に禁欲的で、当初エヴァにも興味を示さなかったようだが、次第に彼女の魅力のとりこになっていく。エヴァは彼の気を惹くため何度も自傷行為を繰り返した。
そもそもヒトラーは画家志望の青年だったが、その愛人エヴァは写真館に勤めていた。フランスの画家・ロートレックの愛人シュザンヌが、ロートレック同様に病んでいた例を思えば、ヒトラーは政治家というよりアーティスト的な心情から「ヤンデレ」のエヴァに惹かれた気もする。
また一見すると平凡に思えるような女性が病んでしまう経緯には、かつて宮台真司が肯定的に捉えた「援助交際する制服少女」たちが、その後10年を経てメンヘラー化してしまった話にも重なるところがある。
ヒトラーの独裁により熱気を帯びていた時代との共通点は「バブル」だろう。世界征服をたくらんだナチスの野望は、バブル景気さながら数年のうちに水泡と帰した。米ソによって東西に分割統治されたベルリンの壁が崩壊したのも、ちょうどバブルの終焉と同じで、それは昭和の終りとも重なっており、ヒトラーのナチ政権は昭和初期と地続きでもある。
55年に及んだ日本の自民党政権も海外では独裁政権として捉えられていたようだが、東日本大震災を経て、民主党はもとより自民党の問題点も明らかにされ、新たな政治が求められている。
それは決してバブル的なものであってはならない。それこそエヴァのように平凡な幸せを願う普通の人が普通に暮らせる社会であってほしい。もともとヒトラーからしてあまりにも普通すぎる夢と野心に満ちた普通の男だったのだ。
日本史の黎明期に存在したとされる邪馬台国の卑弥呼も、人前に顔を見せることはなかったという。そういう点でエヴァには、陰で権力を支える巫女的な体質が感じられるし、実際にその最後は、ヒトラーと結婚した翌日に自害することによって、彼に未来のないことを身を持って知らせた。
そこには浮気される前に幸せなまま死ぬたいと願う、平凡な人間の独占欲もあったかもしれない。けれどもヒトラーはエヴァの思惑通り、彼女の後を追うようにして自殺することとなった。けっきょく非凡なエヴァの前でかの有名な独裁者は、夢見がちな普通の男として世を去ったのだ。
著者についても説明しておこう。ハイケ・B・ゲルテマーカーは1964年生まれの歴史学者の女性。つまり戦後産まれなので、今なお現存する様々な資料を駆使して、本書を上梓したことになる。巻末に付された「注」は35ページ「文献リスト」は25ページにも及び、この評伝の奥深さを示している。
翻訳者の酒寄進一は1958年生まれで、やはり終戦後に産まれ、1979年にドイツ留学を経験。以降ドイツ文学者として小説から評伝まで数多くの翻訳を手がけ、現在は和光大学の教授でもある。
「訳者あとがき」によると、終戦70年に当たる2015年には、現行ドイツの著作権が70年のため、終戦と共に落命したヒトラーの著作権も消滅するが、これまで国内で出版されることのなかった著作が保護されなくなることによって、どういうことになるか気になっていたそうである。
そんな中2010年にドイツで出版された本書は、かつては凡庸と思われていたエヴァの非凡さと、人間としてのヒトラーを暴く視点からテレビのドキュメンタリーの題材にも使われていて、今では「最もスタンダードなエヴァ・ブラウン論」として知られているとのことである。
戦中派の孫の世代に当たる著者は二十代の頃に「ナチ問題をどう歴史的に位置づけるか」という、「歴史家論争」を体験していて、それから二十年を経て自分なりの答えを出したのが本書だと言う。そういう背景から今後ナチについて考える際に重要な意味を持つ必読書のようである。
なお私事で恐縮だが、訳者が教授を務める和光大学は僕の母校であり、18年前の1994年に面接と小論文のみの社会人推薦で入学していて、その時に出題されたのは今や普通に使われている「ロボット」という造語を産んだ、チェコの作家カレル・チャペックによる戯曲『R.U.R.』の抜粋を読んで答える内容で、何かの理由で読んでいた当時のドイツ社会に関する新書を関連づけて論じた覚えがある。
その書名は忘れてしまったが、ベンツやBMWなど高級車メーカーを擁するドイツでは、制限速度のない「アウトバーン」がある一方で、車道と歩道は見事に分断されていて、東京のように狭い通路をヒトとクルマが行き交うようなことは全くなくて安全であり、それに加え「緑化政策」にも力が注がれ、福祉も充実するユートピアのような国だと説明されていた。
チャペックは第一次世界大戦の最中にヒトラーのナチズムを批判していたが、第二次世界大戦の始まった1939年の前年、肺炎により48歳で既に亡くなっていた。けれども彼が『R.U.R.』などで投げかけた、ロボットがヒトに歯向かう設定は、その後も多くの作家に多大な影響を及ぼし、ナチ問題を考える上でも無視できないものだ。
ドイツの戦争責任への過剰なまでの対応は徹底していて、そのことは良く日本とも比較されるが、そのようにしてヒトや地球に優しい国家に生まれ変わった今から振り返ってみると、ヒトラー及びナチズムが反面教師となったからこそ変わることができたとも考えられ、その歴史的位置づけは単に狂っていたと反省するだけでいいのか、判断が難しいように思われる。確かそんなことを書いた覚えがあって、本書もまた日本を考える上でも重要ではないだろうか。
さきほど「母校」と書いたけれど実際には4年間通って退学している。それはさておき、その途中に当たる1995年といえば、今なお映画でリメイクされ続けているテレビアニメ『新世紀エヴァンゲリオン』が放映された年だ。今の日本で「エヴァ」と聞けば、ヒトラーの愛人よりアニメを思い浮かべる人が多いだろう。
実はそのアニメの方の「エヴァ」もヒトラーに関係するところがあって、それは何かというと、ヒトラーが持っていたとされる権力の象徴「ロンギヌスの槍」が作中にも登場する点だ。もともとは十字架の上で処刑されたイエス・キリストの死を確かめるため、その横腹を刺したローマ兵・ロンギヌスの槍が聖なる力を得て今も残っているとの伝説から来ている。
それはあくまで都市伝説的なオカルト話だけれど、SF作品の『新世紀エヴァンゲリオン』では、他にも「死海文書」などオカルトめいた小道具が頻出していて、その世界観はその後に続いた「セカイ系」と呼ばれる多くのアニメや漫画や小説群にも継承されていて、荒唐無稽さという点では、ユダヤ人の大虐殺など余りにも粗暴だったナチ政権の問題行動に通じるところがある。
テレビ版と旧映画版『新世紀エヴァンゲリオン』の主人公シンジにとってのヒロインは二人いるが、そのうちアスカは母親に自殺されたトラウマを持ち、レイはシンジの母親ユイのクローンと、いずれも母娘の複雑な関係が投影されている物語だった。そう考えてみると女性に関心の薄かったはずのヒトラーがエヴァに惹かれたのも、彼あるいは彼女の母親が関係している気もしてくる。
本書ではヒトラーの女性蔑視的な態度に対して、むしろ母性をくすぐられる女性信奉者も数多くいて、そのことが更に周囲の男たちをも魅了することに繋がったという流れも説明されている。ヒトラーの母親クララは1907年、乳がんにより47歳で他界していて、彼はまだ18歳だった。
ヒトラーは愛する母親の死を酷く悲しんでいて、そういう点から鑑みるにエヴァには、母親に近しいところがあったのではないかと察せられる。それをアニメのエヴァにたとえるなら、彼の手にした「ロンギヌスの槍」とは、彼の愛したエヴァ・ブラウン自身だったのかもしれない。